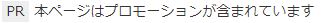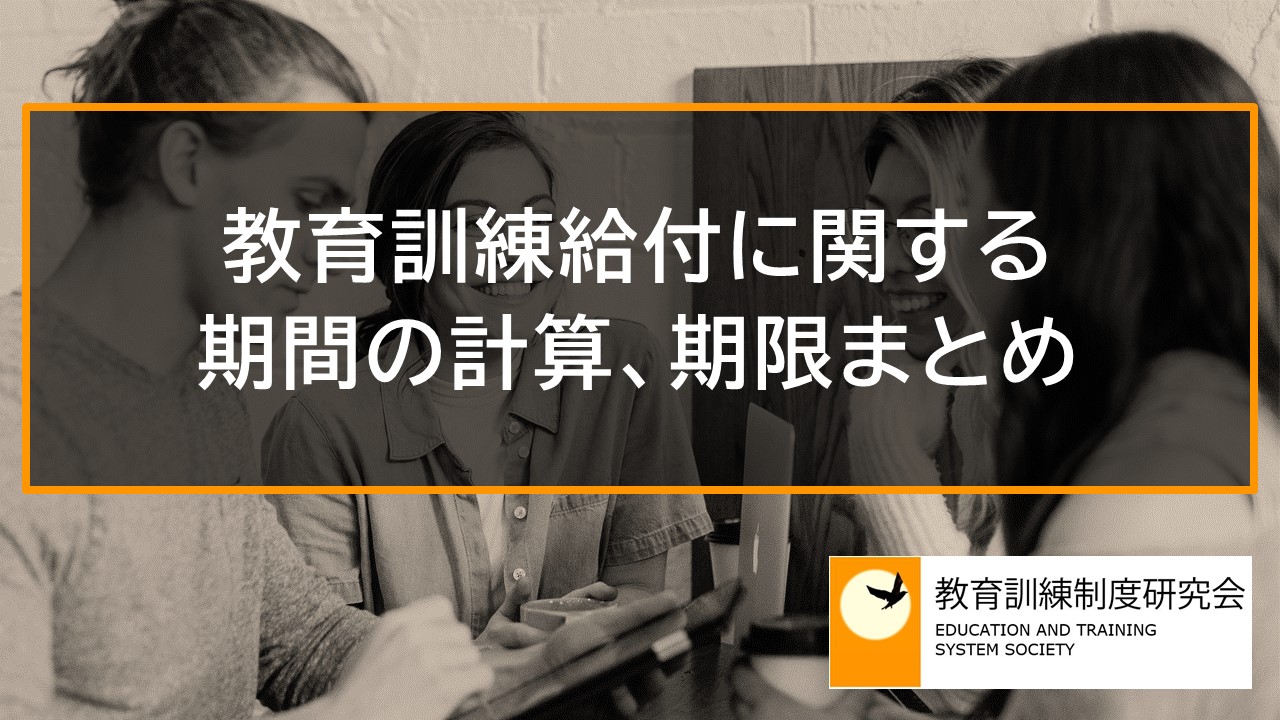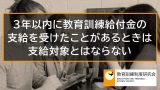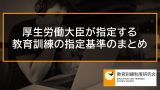教育訓練給付制度には支給対象期間、適用対象期間のほか被保険者の加入に関する期間や申請期限などの期限があります。
1.期間、期限まとめ
支給申請期限は1か月以内、受給資格確認は14日前、未支給の申請期限は6か月以内、給付金の支給は決定翌日から7日以内です。
支給申請期限
支給申請期間は、給付金の申請ができる期間です。
- 一般教育訓練給付金
一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内 - 特定一般教育訓練給付金
特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内 - 専門実践教育訓練給付金
支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内(ハローワークが指示する日) - 専門実践教育訓練給付金の追加給付
追加給付の条件を満たした日の翌日から起算して1か月以内 - 教育訓練支援給付金の支給申請日・ハローワーク出頭日
支給単位期間の末日の翌日から起算して1か月以内で指示される失業認定日 - 未支給の教育訓練給付の支給申請期限
死亡した日の翌日から起算して6か月以内
専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の支給申請期限について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して「1か月以内」で支給申請するよう指示されます。ただし、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が、教育訓練支援給付金の失業認定を受ける場合、可能な限りハローワークが指示した失業認定日に専門実践教育訓練給付金の支給申請を行います。
雇用保険に関する業務取扱要領(行政手引)58217(抜粋)
専門実践教育訓練給付金の支給は、応当日により区切られた6か月(支給単位期間)を単位として、支給要件を判断する。
管轄安定所は、専門実践教育訓練受講予定者に対して、専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、各支給単位期間ごとに支給申請期間(当該支給単位期間の末日の翌日から起算して1ヵ月以内)に支給申請を行うよう指示を行う。
ただし、専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練支援給付金の受給資格者でもある場合、教育訓練支援給付金の失業の認定日を指示することになるため、可能な限りこの日に専門実践教育訓練給付金の支給申請を行うよう指導する。
給付金申請の消滅時効は、権利を行使できるときから2年を経過するまでですが、権利が行使できるのも「翌日」です。
- 一般教育訓練給付金の時効
一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して2年以内 - 特定一般教育訓練給付金の時効
特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して2年以内 - 専門実践教育訓練給付金の時効
支給単位期間の末日の翌日から起算して2年以内 - 専門実践教育訓練給付金の追加給付の時効
追加給付の条件を満たした日の翌日から起算して2年以内 - 教育訓練支援給付金の時効
支給単位期間の末日の翌日から起算して2年以内 - 未支給の教育訓練給付の時効
死亡した日の翌日から起算して2年以内
給付金の支給日
支給決定日はハローワークが支給すると決定した日で、支給日は実際に給付金が振り込まれる日です。
- 教育訓練給付金、未支給教育訓練給付の支給日
ハローワークが支給を決定した日の翌日から起算して7日以内 - 教育訓練支援給付金の支給日
ハローワークが失業を認定した日の翌日から起算して7日以内
受給資格確認票の提出期限日
受給資格確認は、教育訓練の受講開始の前に受給資格を確認する手続きで、開始14日前までに終わらせる必要があります。
- 特定一般教育訓練給付金の受給資格確認
特定一般教育訓練を開始する日の14日前まで - 専門実践教育訓練給付金の受給資格確認
専門実践教育訓練を開始する日の14日前まで - 教育訓練支援給付金の受給資格確認
専門実践教育訓練を開始する日の14日前まで - 受講開始直前に離職した場合の教育訓練支援給付金の受給確認
離職した日の翌日から1か月を経過する日まで
適用対象期間
適用対象期間は、離職者が教育訓練給付金を受ける場合の、離職日から受講開始日までの期間です。
- 適用対象期間
直前の一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から1年以内 - 適用対象期間の最大延長
直前の一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から20年を経過する日まで - 教育訓練支援給付金の最大延長
直前の一般被保険者・高年齢被保険者でなくなった日から4年以内
支給要件期間の空白期間
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。雇用された期間が連続していない期間が1年以内でなければ通算されません。
- 支給要件期間
受講開始日までの間(受講開始日も含む)に同一の事業主に被保険者として雇用された期間- 原則として3年以上
- 初回の場合は一般、特定一般は1年以上、専門実践は2年以上
- 空白期間
直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日の前日から1年以内
給付制限
支給要件期間にかかわらず、過去3年以内に支給を受けたことがあるとき、教育訓練給付金を受給できません。「支給を受けたことがあるとき」の基準は、受講開始日ではなく支給決定日です。
- 3年間給付制限
受講開始日の前日から起算して3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき(最終の支給決定日が3年以内)
支給単位期間
支給単位期間は、専門実践教育訓練の訓練期間を区切って給付金の計算をする期間であり、給付金が支給される期間でもあります。
各支給単位期間は受講開始日に応当する日(なければ月末)から開始します。支給単位期間の末日はその前日となります。
- 専門実践教育訓練給付金の支給単位期間の開始日
受講開始日から起算して6か月ごとに応当する日 - 専門実践教育訓練給付金の支給単位期間の末日
受講開始日から起算して6か月ごとに応当する日の前日 - 教育訓練支援給付金の支給単位期間の開始日
受講開始日から起算して2か月ごとに応当する日 - 教育訓練支援給付金の支給単位期間の末日
受講開始日から起算して2か月ごとに応当する日の前日
支給限度期間
支給限度期間は、専門実践教育訓練給付金を複数回受給する場合の10年間の上限を定める期間です。支給限度期間(10年)で上限額があるとともに、支給限度期間(10年)のなかで4年課程の上乗せが1回に限られます。
- 支給限度期間
初回の受講開始日から起算して10年を経過する日までの期間(経過した後も同様に10年の支給限度期間がある)
指定期間
指定期間は、厚生労働大臣の指定が有効である期間、教育訓練給付対象講座としての有効期間です。
講座指定は年に2回行っています。指定期間は、4月1日または10月1日から3年間です。
2.起算日、期間の計算
翌日から起算する期間の計算
教育訓練給付金の支給申請期限は通常、申請できるようになった日の「翌日から1か月間」です。
修了日に何らかの学校行事があったとしても修了日当日を除いて確実に1か月間を確保できるように「翌日」から起算しています。もちろん修了日当日に手続きをしてもかまいません。さらに、申請期限の末日が行政機関の休日(日曜祝日と土曜と年末年始)に当たるときは休日明けの日が期間満了日となります。
修了日が月末の場合
修了日が月末の場合は、その翌月の1か月間となります。
例えば、修了日が5月31日の場合、修了日の翌日は6月1日で申請期限は6月30日です(応当日である7月1日の前日)。申請できる期間は5月31日から6月30日までです。
修了日が月末以外の場合
修了日が月末以外の場合は、修了日の翌月の応当日までで応当日が無い場合は翌月末までとなります。
例えば、修了日が5月30日の場合、修了日の翌日は5月31日で申請期限は翌月6月30日です(応当日の6月31日が無いので月末)。申請できる期間は5月30日から6月30日までです。
行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日法律第91号)第2条
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
民法 第143条第2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
翌日から起算する期間
離職日、一般被保険者でなくなった日、被保険者資格の喪失日は通常、退職した日の翌日です。例えば、退職が3月31日なら、離職日(資格喪失日)は4月1日です。これらの日から起算する場合も「翌日から起算する期間」です。
さかのぼる期間の計算
さかのぼる期間の場合も「当日」か「前日」を起算日にします。
例えば、「4月1日の1か月前まで」は、当日を起算日にすると1か月前は3月2日になります(応当日の翌日、応当日が無い時は月末)。期限の場合は3月2日午前0時までと解釈し、さらに1日さかのぼって「3月1日(24時)まで」となります。
通常は前日を起算日にします。前日を起算日にすると前日が3月30日なのでその1か月前は3月1日になり、期限の場合はさらに1日さかのぼって「2月末まで」となります。
3.補足説明
1年間の計算方法、年齢の計算方法について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。