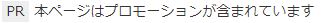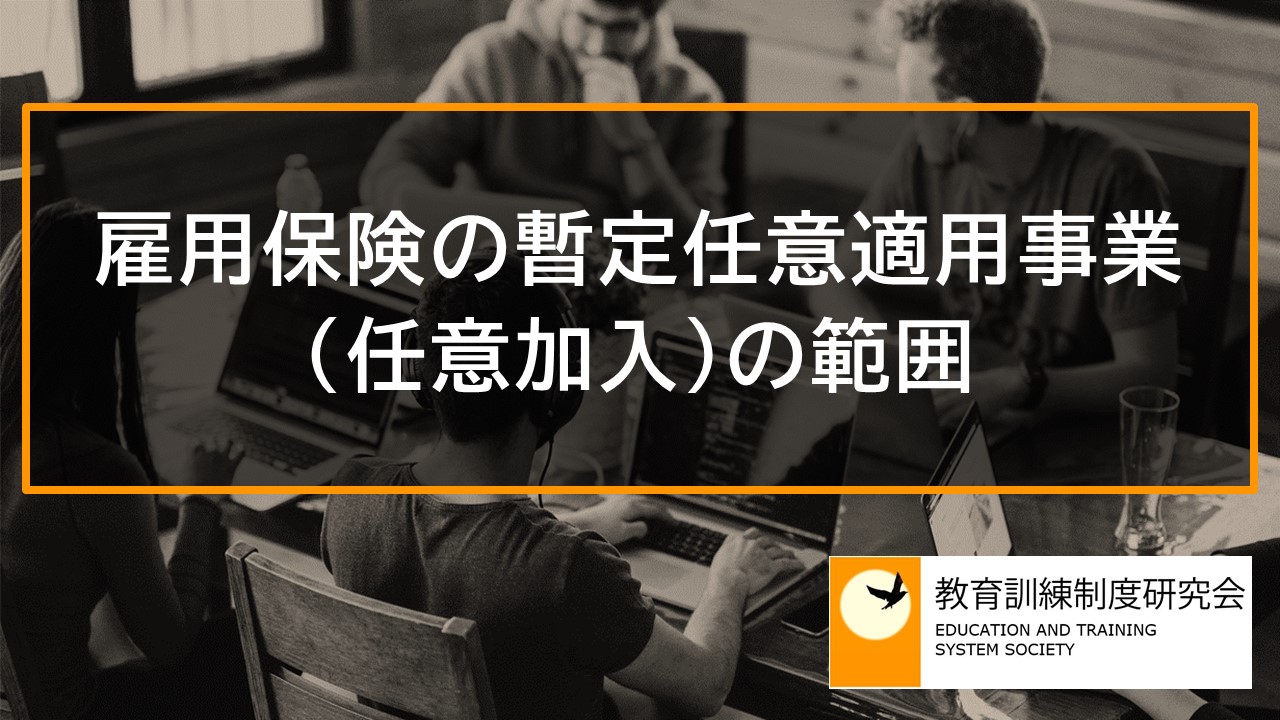雇用保険は、個人単位ではなく事業単位で適用されます。「雇用保険適用事業」とは雇用保険が適用される事業です。適用事業の事業主は、雇用保険料の納付と各種の届出等の義務を負います。
1.強制適用(当然適用)の原則
事業のうち、原則として労働者を1人でも雇用していれば業種のいかんを問わず、法律上、当然に、雇用保険の対象となり、雇用保険の加入義務があります。事業全体に対して適用されるので、雇われている労働者は個別の意思にかかわらず全員適用され、雇用保険法第6条に該当する者を除き被保険者となります。
雇用保険法 第5条第1項
この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
ただし、雇われている労働者がすべて雇用保険法第6条(適用除外)に該当する場合には、当該事業は適用事業とはなりません。
2.暫定任意適用事業
暫定任意適用事業
暫定任意適用事業とは、本来雇用保険が強制的に適用されるはずの事業のうち、雇用保険に加入する前に事業主と労働者の同意を要することとされている零細事業のことです。労働者の2分の1以上の同意を得て、事業主が任意加入の申請をした時に保険関係が成立します。
農林水産の事業のうち一部の事業は、当分の間、任意適用事業(雇用保険暫定任意適用事業)とされています。
雇用保険法 附則第2条第1項
次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。
一 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
二 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
暫定任意適用事業の制度の理由
農林水産業の事業については事業所の把握が困難な場合が多く、雇用関係、賃金支払い関係が必ずしも明確ではない場合が多いです。季節や時期によって労働人数や労働時間に偏りが激しく、強制適用すると事務的に困難であり、実効性が乏しいことから、これらの事業については任意加入制度により対処することとしています。
当分の間(暫定措置)ということになっていますが、雇用保険法ができた1974年(昭和49年)当時からこの制度はあったので、50年以上改正されていないことになります(改正する気はないのでしょう)。
3.暫定任意適用事業となる条件
暫定任意適用事業である条件は、次のすべてを満たす場合をいいます。
- 農林水産業であること
- 個人経営であること
- 労働者が常時5人以上でないこと
雇用保険法施行令 附則第2条第1項
法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。
農林水産業であること
任意適用となる農林水産の事業とは次の事業のことです。ただし、船員が雇用される事業を除きます。
- 農業、林業:土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(農業用水供給業及びもやし製造業を除く)
- 畜産業、養蚕業、水産業:動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)
農業用水供給業、かんがい用水供給業は、日本標準産業分類では「農業、林業→農業サービス業→かんがい用水供給業」に含まれますが、雇用保険法上は農業ではなく、水道業(上水道業)として強制適用事業となります。
もやし製造業は、以前は日本標準産業分類では「製造業→食品製造業→もやし製造業」とされていましたが、2002年(平成14年)の改訂により「農業→野菜作農業→もやし栽培農業」に分類されることになり、もやし=農産物として扱われることになりました。しかし、雇用保険法上は農業ではなく、食品製造業として強制適用事業となります。
個人経営であること
個人経営とは、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものおよび法人の事業を除いた個人で営む事業のことです。
「国、都道府県、市町村に準ずるもの」とは、具体的には地方自治法で定める「特別地方公共団体」のことです。
- 特別区
- 地方公共団体の組合
- 産区及び地方開発事業団
- 港湾法に基づいて設立された港務局
「法人」とは、私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人(会社)を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれます。ただし、法人である事業主の事業は強制適用となるのはその事務所に限られます。それは、現場部門は法律上、任意適用事業となる可能性があるためです。
労働者が常時5人以上でないこと
常時5人以上の労働者を雇用する事業は強制適用となり、労働者が5人未満となることがあれば任意適用事業となります。
この「労働者」には、雇用保険法第6条に該当し法の適用を受けない労働者(被保険者とならない労働者)も含まれます。したがって、被保険者ではない日雇労働者なども含めて計算します。ただし、法の適用を受けない労働者(被保険者とならない労働者)のみを雇用する事業については、被保険者がいないので「適用事業として取り扱う必要はない」とされています。
「常時5人以上」とは、労働者が年間を通じて5人以上であることをいいます。したがって、次の場合は「常時5人以上」には該当しないので、任意適用事業となります。
- ごく短期間のみ行われる事業
- 季節的事業(一定の季節にのみ行われる事業)
- 年間を通じて行われる事業であっても、事業が季節の影響を強く受け、ある一定期間は労働者が5人未満に減少することが通例である場合
ただし、労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱うこととされています。
4.事業主が複数の事業をしている場合
事業主が複数の事業をしている場合、労働者の人数は事業単位で数えます。
事業主が適用事業に該当する部門(適用部門)と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合、それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となります。しかし、一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となります。
5.暫定任意適用事業の任意加入の申請
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、任意加入の申請をする場合、労働者の2分の1以上の同意を得たうえで、任意加入申請書をその事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出します。
なお、労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は任意加入の申請をしなければなりません。
同意を要する「労働者の2分の1」とはその事業において使用される労働者総数の2分の1ではなく、雇用保険法第6条に該当しない労働者(被保険者となる労働者)の2分の1です。例えば、労働者4人のうち被保険者となりうる労働者が2人であれば、その2分の1は1人となります。被保険者となる者であるかどうかの判断は、任意加入申請書の提出の時点で行います。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)附則第2条第1~3項
雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。
3 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。
6.任意加入の効果
保険関係の成立
暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立します。保険関係が成立したら、当該事業に雇用される者全員に適用されますから、任意加入の同意をしなかった労働者にも適用されます。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第4条
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)附則第3条
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するに至つた場合における第四条の規定の適用については、その該当するに至つた日に、その事業が開始されたものとみなす。
被保険者
保険関係が成立した後は、通常の適用事業と同じ扱いとなります。そのため、任意加入の認可を受けた事業に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります。雇用保険法第6条の規定に該当する労働者が適用除外になるのも同じです。
7.任意加入・強制加入の変更
強制加入→任意加入
適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員等によって、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされます(擬制任意適用事業)。
この場合は、法律上当然に任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業とみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続や届け出を行う必要はありません。また、労働者が被保険者であることに変わりはないので、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことについての確認の手続も必要ありません。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)附則第2条第4項
雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。
任意加入→強制加入
任意加入の認可を受けて、雇用保険に係る保険関係が成立している事業(雇用保険が適用されている事業)は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業に含まれます。つまり、保険関係が成立した後は、通常の適用事業と同じ扱いとなります。任意加入の時に手続きをしているので、その後、強制適用事業に該当することとなったとしても特に手続きは不要です(事業内容に変更があれば変更届を提出する)。
雇用保険法 附則第2条第2項
前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、徴収法附則の定めるところによるものとし、徴収法附則第二条又は第三条の規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第五条第一項に規定する適用事業に含まれるものとする。
暫定任意適用事業で任意加入の認可を受けていない事業(雇用保険が適用されていない事業)が、強制適用事業に該当するに至った場合、その該当するに至った日に保険関係が成立します。この場合は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届や雇用保険適用事業所設置届の提出が必要となります。
8.任意加入の消滅
任意加入の保険関係を消滅させるには、事業主が労働者の4分の3以上の同意を得て、暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をします。厚生労働大臣の認可のあった日の翌日に雇用保険に係る保険関係が消滅します。
保険関係の消滅の認可があった場合に、その事業に雇用される被保険者は、その認可のあった日の翌日から被保険者でなくなるので、事業主は、その事業に雇用される被保険者について雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)附則第4条
附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
2 前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、保険関係はその翌日に消滅します。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第5条
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
9.補足
労災保険、他の社会保険について
雇用保険以外の、労働保険(労災)や他の社会保険にも任意適用事業の制度がありますが、それぞれ制度が異なります。雇用保険で任意適用であったとしても、他の保険制度で任意適用であるとは限りません。